Magical Bone Sticksは、ちょっとした効果を持つ杖を3本付け加えるMODです。
まず素材として、インク、金インゴット、骨のみっつで金メッキの骨(Gilded Bone)を作成します。

その後、金メッキの骨*2とTNTでBam Stick、金メッキの骨*2とスライムボールでJump Stick、金メッキの骨*2と鉄ブロックでLightning Stickの3種類の杖ができあがります。



Bam Stickの効果は文字通りというか素材通り。

使用回数は8回。
右クリックで大爆発、床に大穴を空けます。消費回数は2。
左クリックで攻撃した敵を爆殺し、その影響で小さな穴も空きます。消費回数1。
幸いなことに、いずれにせよプレイヤーはダメージを受けません。
Jump Stickの効果も名前のとおり。
使用回数は64回。
敵に向かって左クリックで、敵やモブを空高く投げ上げます。消費回数2。

飛行能力がないかぎり墜落死は免れないことでしょう。
地面に向かって右クリックでこんどは自分を投げ上げます。
こちらの場合は落下ダメージはありませんが、ジャンプする高さも6ブロック程度となります。
ちなみにJump Stickでジャンプした際の落下ダメージは完全にキャンセルされるので、ジャンプして縦穴に落ちると無傷で降りることができます。
最後にLightning Stickですが、やはり名前のとおりです。
使用回数は8回。
左クリックで対象の敵に向かって電撃攻撃、消費回数1。
右クリックで5ブロック以内の敵に範囲攻撃、消費回数3。
電撃なので、当然クリーパーや豚に使うと大変なことになります。
さて次はGodStick、神の棒です。
うむ、いかにも厨二らしい名称だ。
って今見たら消えてますね。残念。まあどうしても入れたければ探してください。
まず素材として、金インゴット*3でblank GODSTICK。

そしてblank GODSTICK+鉄インゴット+水バケツでwater GODSTICK、blank GODSTICK+鉄インゴット+溶岩バケツでlava GODSTICK、blank GODSTICK+鉄インゴット+雪玉でsnow GODSTICKと3種類の棒ができあがります。



効果のほども想像通り、水源、溶岩源、雪を生み出すものとなっています。
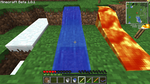
特にバケツを用意せずにほいほい設置できるため、トラップタワーなどの設置に便利なアイテムです。
ただしこの杖では設置した水源・溶岩源の回収はできないので、誤設置には注意しましょう。
使用回数はおそらく64回です。
マインクラフトのまとめ
まず素材として、インク、金インゴット、骨のみっつで金メッキの骨(Gilded Bone)を作成します。
その後、金メッキの骨*2とTNTでBam Stick、金メッキの骨*2とスライムボールでJump Stick、金メッキの骨*2と鉄ブロックでLightning Stickの3種類の杖ができあがります。
Bam Stickの効果は文字通りというか素材通り。
使用回数は8回。
右クリックで大爆発、床に大穴を空けます。消費回数は2。
左クリックで攻撃した敵を爆殺し、その影響で小さな穴も空きます。消費回数1。
幸いなことに、いずれにせよプレイヤーはダメージを受けません。
Jump Stickの効果も名前のとおり。
使用回数は64回。
敵に向かって左クリックで、敵やモブを空高く投げ上げます。消費回数2。
飛行能力がないかぎり墜落死は免れないことでしょう。
地面に向かって右クリックでこんどは自分を投げ上げます。
こちらの場合は落下ダメージはありませんが、ジャンプする高さも6ブロック程度となります。
ちなみにJump Stickでジャンプした際の落下ダメージは完全にキャンセルされるので、ジャンプして縦穴に落ちると無傷で降りることができます。
最後にLightning Stickですが、やはり名前のとおりです。
使用回数は8回。
左クリックで対象の敵に向かって電撃攻撃、消費回数1。
右クリックで5ブロック以内の敵に範囲攻撃、消費回数3。
電撃なので、当然クリーパーや豚に使うと大変なことになります。
さて次はGodStick、神の棒です。
うむ、いかにも厨二らしい名称だ。
って今見たら消えてますね。残念。まあどうしても入れたければ探してください。
まず素材として、金インゴット*3でblank GODSTICK。
そしてblank GODSTICK+鉄インゴット+水バケツでwater GODSTICK、blank GODSTICK+鉄インゴット+溶岩バケツでlava GODSTICK、blank GODSTICK+鉄インゴット+雪玉でsnow GODSTICKと3種類の棒ができあがります。
効果のほども想像通り、水源、溶岩源、雪を生み出すものとなっています。
特にバケツを用意せずにほいほい設置できるため、トラップタワーなどの設置に便利なアイテムです。
ただしこの杖では設置した水源・溶岩源の回収はできないので、誤設置には注意しましょう。
使用回数はおそらく64回です。
マインクラフトのまとめ
PR
なんかいつも設定のどこかを忘れてひっかかるので最低限必要な部分だけ書いておくメモ。
なお、単に自分のサーバで送受信するだけであればsendmail.mcとかはデフォルトのまま変更する必要はありません。
と思うんだけど、メール関連で踏み台とかセキュリティホールとかよく見るので、本当は何か必要なのかも?
よくわからないので誰か教えてください。
例としてinfo@example1.com、info@example2.com宛のメールを受信する設定を行います。
DNSとかは別途設定が必要なのでまあ適当にやって下さい。
/etc/mail/local-host-names
自分のサーバで受け取るメールのドメインを指定します。
ここに書いてあるものは/etc/mail/virtusertableに、書いていないものは/etc/mail/accessにと振り分けられる、メール取扱いの入口です。
書式は、単にドメイン名を羅列します。
example1.com
example2.com
/etc/mail/access
自分のサーバ宛て以外のメールを受け取ったときの動作。
初期設定は以下のようになっています。
localhost.localdomain RELAY
localhost RELAY
127.0.0.1 RELAY
「ローカルホストから送付されたメールのみ、他のサーバに転送を許可する」という意味です。
下手に設定するとスパムの発信基地にされたりしてしまうみたいなので、基本的にデフォルトのままにします。
/etc/mail/virtusertable
完全なメールアドレスでメールの宛先を変更します。
info@example1.com、info@example2.com宛のメールは、どちらもinfoユーザ宛に届きます。
両方とも同じユーザ宛でいいのであれば何も書かなくてよいですが、別のユーザに振り分けたいときに設定します。
info@example1.com info_example1
info@example2.com info_example2
これでinfo@example1.com宛のメールはinfo_example1ユーザに、info@example2.com宛のメールはinfo_example2ユーザに届くようになりました。
特に振り分けせずにそのままでいいよ、という場合は何も記述しません。
/etc/aliases
ユーザに届いたメールを転送します。
こちらはvirtusertableとちがってユーザ単位でしか設定できないみたいですが、そのかわり複数ユーザに転送などができます。
何故かこれだけ/etc/mail/の外なので注意。
info_example1: hoge, fuga
info_example2: info@example3.com
info_example1ユーザ宛のメールはhogeユーザとfugaユーザ宛に、info_example2ユーザ宛のメールはinfo@example3.comのメールアドレスに送付されます。
こちらも変更しない場合は何も記述しません。
上記を全部合わせると、info@example1.com宛のメールはhogeユーザとfugaユーザ宛に、info@example2.com宛のメールはinfo@example3.comのメールアドレスに送られるということになります。
なお、local-host-names以外は編集後にリフレッシュコマンドが必要です。
makemap -v hash /etc/mail/access.db < /etc/mail/access
/usr/sbin/makemap hash /etc/mail/virtusertable.db < /etc/mail/virtusertable
newaliases
なお、単に自分のサーバで送受信するだけであればsendmail.mcとかはデフォルトのまま変更する必要はありません。
と思うんだけど、メール関連で踏み台とかセキュリティホールとかよく見るので、本当は何か必要なのかも?
よくわからないので誰か教えてください。
例としてinfo@example1.com、info@example2.com宛のメールを受信する設定を行います。
DNSとかは別途設定が必要なのでまあ適当にやって下さい。
/etc/mail/local-host-names
自分のサーバで受け取るメールのドメインを指定します。
ここに書いてあるものは/etc/mail/virtusertableに、書いていないものは/etc/mail/accessにと振り分けられる、メール取扱いの入口です。
書式は、単にドメイン名を羅列します。
example1.com
example2.com
/etc/mail/access
自分のサーバ宛て以外のメールを受け取ったときの動作。
初期設定は以下のようになっています。
localhost.localdomain RELAY
localhost RELAY
127.0.0.1 RELAY
「ローカルホストから送付されたメールのみ、他のサーバに転送を許可する」という意味です。
下手に設定するとスパムの発信基地にされたりしてしまうみたいなので、基本的にデフォルトのままにします。
/etc/mail/virtusertable
完全なメールアドレスでメールの宛先を変更します。
info@example1.com、info@example2.com宛のメールは、どちらもinfoユーザ宛に届きます。
両方とも同じユーザ宛でいいのであれば何も書かなくてよいですが、別のユーザに振り分けたいときに設定します。
info@example1.com info_example1
info@example2.com info_example2
これでinfo@example1.com宛のメールはinfo_example1ユーザに、info@example2.com宛のメールはinfo_example2ユーザに届くようになりました。
特に振り分けせずにそのままでいいよ、という場合は何も記述しません。
/etc/aliases
ユーザに届いたメールを転送します。
こちらはvirtusertableとちがってユーザ単位でしか設定できないみたいですが、そのかわり複数ユーザに転送などができます。
何故かこれだけ/etc/mail/の外なので注意。
info_example1: hoge, fuga
info_example2: info@example3.com
info_example1ユーザ宛のメールはhogeユーザとfugaユーザ宛に、info_example2ユーザ宛のメールはinfo@example3.comのメールアドレスに送付されます。
こちらも変更しない場合は何も記述しません。
上記を全部合わせると、info@example1.com宛のメールはhogeユーザとfugaユーザ宛に、info@example2.com宛のメールはinfo@example3.comのメールアドレスに送られるということになります。
なお、local-host-names以外は編集後にリフレッシュコマンドが必要です。
makemap -v hash /etc/mail/access.db < /etc/mail/access
/usr/sbin/makemap hash /etc/mail/virtusertable.db < /etc/mail/virtusertable
newaliases
磁石を使いまくるプラズマの用途を紹介。
まずプラズマ作成機(Plasmaficator)を作成。
レシピは誘導加熱炉、合金板*4、カーボンプレート*4。

この機械はプラズマを作成してくれますが、素材となるのはなんとダイヤモンドです。
消費電力は32EU/tで安定稼働してくれるようですが、作成がかなりゆっくりなため、相当な電力を消費します。
きっちり計ったわけではありませんが、プラズマひとつにつきおよそ30万EUくらい?

なおHeatが上がると作成時間がすこし減少しますが、それでも待っていられるレベルの時間ではないので、他のことをするなり放置して風呂にでも行くなりしましょう。
次に磁力バキュームボトル(Maginetic Vacuum Bottle)。
Vacuum Bottleは魔法瓶らしいので、和訳すると磁力魔法瓶?
ひでえ訳だな。
ということでなんかいい訳教えてください。
レシピは磁石*4、カーボンプレート*4。

磁力魔法瓶をプラズマ*8で囲むとプラズマバキュームボトル(Plasma Vacuum Bottle)。

こいつがプラズマデバイスのメイン素材となります。
磁石16個、ダイヤモンド8個からようやくこれがひとつできるという効率のよさ。
ちなみにここで一点注意があります。
Plasmaficatorを設置したままログアウトすると、そのチャンクが初期化されます。
いや致命的すぎるだろそのバグ。
機械が消えるとかそういうレベルの生やさしいものではなく、一帯が完全に消滅してしまうのでうっかり発電施設の真ん中で発動したりしようものなら大惨事です。
フォーラムにもちらほら報告が上がってますが、作者は「IC2の正式版対応までアップデートしねえ、嫌なら使うな」とか言ってます。ファック!
なおPlasmaficatorを設置せずにインベントリやチェストに入れておいたままであれば大丈夫です。
こいつを使うときはログアウト前に毎回回収し、また念のために消えても問題ないチャンクまでケーブルをひっぱって使用しましょう。

マインクラフトのまとめ
まずプラズマ作成機(Plasmaficator)を作成。
レシピは誘導加熱炉、合金板*4、カーボンプレート*4。
この機械はプラズマを作成してくれますが、素材となるのはなんとダイヤモンドです。
消費電力は32EU/tで安定稼働してくれるようですが、作成がかなりゆっくりなため、相当な電力を消費します。
きっちり計ったわけではありませんが、プラズマひとつにつきおよそ30万EUくらい?
なおHeatが上がると作成時間がすこし減少しますが、それでも待っていられるレベルの時間ではないので、他のことをするなり放置して風呂にでも行くなりしましょう。
次に磁力バキュームボトル(Maginetic Vacuum Bottle)。
Vacuum Bottleは魔法瓶らしいので、和訳すると磁力魔法瓶?
ひでえ訳だな。
ということでなんかいい訳教えてください。
レシピは磁石*4、カーボンプレート*4。
磁力魔法瓶をプラズマ*8で囲むとプラズマバキュームボトル(Plasma Vacuum Bottle)。
こいつがプラズマデバイスのメイン素材となります。
磁石16個、ダイヤモンド8個からようやくこれがひとつできるという効率のよさ。
ちなみにここで一点注意があります。
Plasmaficatorを設置したままログアウトすると、そのチャンクが初期化されます。
いや致命的すぎるだろそのバグ。
機械が消えるとかそういうレベルの生やさしいものではなく、一帯が完全に消滅してしまうのでうっかり発電施設の真ん中で発動したりしようものなら大惨事です。
フォーラムにもちらほら報告が上がってますが、作者は「IC2の正式版対応までアップデートしねえ、嫌なら使うな」とか言ってます。ファック!
なおPlasmaficatorを設置せずにインベントリやチェストに入れておいたままであれば大丈夫です。
こいつを使うときはログアウト前に毎回回収し、また念のために消えても問題ないチャンクまでケーブルをひっぱって使用しましょう。
マインクラフトのまとめ
これまでソーラー以外の発電機について華麗にスルーしてきましたが、せっかくなので作ってみることにします。
まず水力発電機は火力発電機、木材*4、棒*4と非常に安価。

そのぶん発電量も非常に控えめです。
燃料として水バケツを使用した場合、発電速度こそ2EU/tとソーラー発電機の倍ですが、水バケツ一個あたりの発電量はわずか1000EUです。
水中に設置することでリソース不要の発電も可能なのですが、最大でもわずか0.25EU/tという非常にささやかな発電量となっています。
ソーラー発電機とちがい夜間も発電可能ではありますが、周囲に水があればあるほど発電量がアップするという仕様のため、ソーラー発電機のようにずらっと並べて発電することができず効率も上がりません。

また最大の問題点として、発電に使用した後の空バケツを木パイプで取り出すことができません。
このせいで自動運転ができず、他の発電機に比べ致命的に扱いにくくなっています。
次に地熱発電機。
レシピは火力発電機、精錬鉄*2、空のセル*2、ガラス*4。

使い方は燃料が溶岩バケツに変わっただけで基本的に水バケツと一緒です。
ただし溶岩中に設置しても発電量は上がりません、というか燃えます。
発電量は燃料が変わったおかげで格段にアップし、発電速度10EU/t、発電量20000EUと、発電速度は5倍、バケツ一個あたり発電量は20倍となっています。
高出力がほしい場合は有力な発電源として検討できそうです。
といっても使用後のバケツを木パイプで取り出せない仕様はそのままなので、やはり自動運転には向かない発電機となっています。
なお、水力/地熱発電機ともに燃料としてバケツのかわりにセルが使えます。
セルは使い捨てかつスタック可能なので、セルの量産をどうにかすれば自動運転できそうです。
最後に風力発電機。
レシピは火力発電機、鉄*4とシンプル。

リソースは不要ですが、他の発電機より設置条件が遙かに厳しく、
・基本的に発電量は安定しない
・位置が低くなると発電量が減る
・発電機の周囲4マスにブロックがあると発電量が減る
となっているようです。
発電量自体は、高度120のあたりに設置すれば3EU/t程度にはなります。
ソーラー発電機とちがい縦に並べることもできるので、グラスファイバーを惜しげ無く使えばかなりの出力を得られるでしょう。
まあ、空中に設置するのがかなり手間なんですがね。

原発はよくわかんないのでパスということでひとつ。
マインクラフトのまとめ
まず水力発電機は火力発電機、木材*4、棒*4と非常に安価。
そのぶん発電量も非常に控えめです。
燃料として水バケツを使用した場合、発電速度こそ2EU/tとソーラー発電機の倍ですが、水バケツ一個あたりの発電量はわずか1000EUです。
水中に設置することでリソース不要の発電も可能なのですが、最大でもわずか0.25EU/tという非常にささやかな発電量となっています。
ソーラー発電機とちがい夜間も発電可能ではありますが、周囲に水があればあるほど発電量がアップするという仕様のため、ソーラー発電機のようにずらっと並べて発電することができず効率も上がりません。
また最大の問題点として、発電に使用した後の空バケツを木パイプで取り出すことができません。
このせいで自動運転ができず、他の発電機に比べ致命的に扱いにくくなっています。
次に地熱発電機。
レシピは火力発電機、精錬鉄*2、空のセル*2、ガラス*4。
使い方は燃料が溶岩バケツに変わっただけで基本的に水バケツと一緒です。
ただし溶岩中に設置しても発電量は上がりません、というか燃えます。
発電量は燃料が変わったおかげで格段にアップし、発電速度10EU/t、発電量20000EUと、発電速度は5倍、バケツ一個あたり発電量は20倍となっています。
高出力がほしい場合は有力な発電源として検討できそうです。
といっても使用後のバケツを木パイプで取り出せない仕様はそのままなので、やはり自動運転には向かない発電機となっています。
なお、水力/地熱発電機ともに燃料としてバケツのかわりにセルが使えます。
セルは使い捨てかつスタック可能なので、セルの量産をどうにかすれば自動運転できそうです。
最後に風力発電機。
レシピは火力発電機、鉄*4とシンプル。
リソースは不要ですが、他の発電機より設置条件が遙かに厳しく、
・基本的に発電量は安定しない
・位置が低くなると発電量が減る
・発電機の周囲4マスにブロックがあると発電量が減る
となっているようです。
発電量自体は、高度120のあたりに設置すれば3EU/t程度にはなります。
ソーラー発電機とちがい縦に並べることもできるので、グラスファイバーを惜しげ無く使えばかなりの出力を得られるでしょう。
まあ、空中に設置するのがかなり手間なんですがね。
原発はよくわかんないのでパスということでひとつ。
マインクラフトのまとめ
引き続きAdvanced Generatorsの紹介。
今回は磁石関連です。
まずレアアース抽出装置(Rare Earth Extractor)。
レシピは抽出機、リサイクル装置、グロウストーンダスト*4。

これに対してソウルサンド、黒曜石、粘土、ネザーラック、丸石の何れかを投入すると、希にレアアースダスト(Rare Earth Dust)が抽出されます。
なお投入する素材によってレアアースダストの回収確率が違い、ソウルサンドであれば64個から5個程度回収できます。
丸石なら5スタック突っ込んで結果が0個だよ、といったことが普通に起こります。
なお、おそらく確率は上記の素材順だと思われます。
ネザーからソウルサンドをありったけ回収してきましょう。
さてレアアースダストの数がある程度揃ったら、それを元手に磁石を作ります。
精錬鉄+レアアースダスト*4でレアアースの塊(Rare Earth Chunk)。
レアアースの塊を圧縮すると死んだ磁石(Dead Magnet)。
死んだ磁石と充電池(満充電)で磁石(Magnet)。



ようやく磁石ができました。
これでやっと前回作れなかった水力、風力発電機を作ることができます。
まず高等水力発電機(Advanced Water Mill)は水力発電機、磁石*4。

周囲を水で埋めることで、0.4EU/t程度で発電することが可能です。

元が0.25EU/tだから倍近くに増えているとはいえ、あんまり嬉しいレベルではありませんね。
ヘルプでは4倍出力するってなってるんだけどそんなにならなかったんだけど本当なのか?
最後に高等風力発電機(Advanced Wind Mill)。
レシピは風力発電機、磁石*2。


最高高度に設置したところです。
風力はランダムで変化しますが、概ね3EU弱/t程度の発電量を常時維持してくれます。
ってあれえ?
元の風力発電機とあまり変わっていないような。
ヘルプではこっちも2倍って書いてあるんですけどね。
風力と水力発電機は単純に元の発電機の性能アップ版なので、素材が余っていれば入れ替えるといいかもしれません。
マインクラフトのまとめ
今回は磁石関連です。
まずレアアース抽出装置(Rare Earth Extractor)。
レシピは抽出機、リサイクル装置、グロウストーンダスト*4。
これに対してソウルサンド、黒曜石、粘土、ネザーラック、丸石の何れかを投入すると、希にレアアースダスト(Rare Earth Dust)が抽出されます。
なお投入する素材によってレアアースダストの回収確率が違い、ソウルサンドであれば64個から5個程度回収できます。
丸石なら5スタック突っ込んで結果が0個だよ、といったことが普通に起こります。
なお、おそらく確率は上記の素材順だと思われます。
ネザーからソウルサンドをありったけ回収してきましょう。
さてレアアースダストの数がある程度揃ったら、それを元手に磁石を作ります。
精錬鉄+レアアースダスト*4でレアアースの塊(Rare Earth Chunk)。
レアアースの塊を圧縮すると死んだ磁石(Dead Magnet)。
死んだ磁石と充電池(満充電)で磁石(Magnet)。
ようやく磁石ができました。
これでやっと前回作れなかった水力、風力発電機を作ることができます。
まず高等水力発電機(Advanced Water Mill)は水力発電機、磁石*4。
周囲を水で埋めることで、0.4EU/t程度で発電することが可能です。
元が0.25EU/tだから倍近くに増えているとはいえ、あんまり嬉しいレベルではありませんね。
ヘルプでは4倍出力するってなってるんだけどそんなにならなかったんだけど本当なのか?
最後に高等風力発電機(Advanced Wind Mill)。
レシピは風力発電機、磁石*2。
最高高度に設置したところです。
風力はランダムで変化しますが、概ね3EU弱/t程度の発電量を常時維持してくれます。
ってあれえ?
元の風力発電機とあまり変わっていないような。
ヘルプではこっちも2倍って書いてあるんですけどね。
風力と水力発電機は単純に元の発電機の性能アップ版なので、素材が余っていれば入れ替えるといいかもしれません。
マインクラフトのまとめ
前回しれっとクァーリーに繋がっていた謎のパイプの正体ですが、Energy Couplerの調整エネルギーパイプです。
ということでEnergy Couplerは、ICの電力をBCのエンジン動力に変換することのできるMODです。
BCのエンジンは、エンジンごとに石炭やオイルの補充が必要なのがネックでしたが、これを使うとBCの機械をエンジンのかわりにEUで動かすことができるようになります。
これで発電機だけを管理すればよくなるため楽になりますね。
さらにソーラー発電機であれば一切の管理が不要になります。
なお、便利なだけあってエネルギー変換効率は低めに設定されています。
さっそく作ってみます。
低圧エネルギー連結器(LV Energy Coupler)はゴム*6、木エネルギーパイプ、充電池、銅ケーブル。
中圧エネルギー連結器(MV Energy Coupler)はゴム*6、木エネルギーパイプ、エナジークリスタル、金ケーブル。
高圧エネルギー連結器(HV Energy Coupler)はゴム*6、木エネルギーパイプ、ラポトロンクリスタル、精錬鉄ケーブル。



効果はまあ名前のとおりで、LVは最大32EU、MVは128EU、HVは512EUを入力し、対応するだけのBCのエネルギーを出力します。
エネルギー連結器のドット1つのほうにICの電力を、ドットが3つのほうにエネルギーパイプを接続し、その先をクァーリーなどBCのマシンに接続すると機械が動作します。

問題点としては、接続先にできるのは機械だけで、エンジンやパイプに対する動力源としては使用できません。
黒曜石パイプの回収範囲を広めるためにはこれまで通りエンジンを使用しなければならないようです。
もうひとつ欠点があり、通常のエネルギーパイプを使用すると常に全力でエネルギーを出力します。
高圧エネルギー連結器の先にエネルギー木パイプをつなげると、たとえその先に機械がなかったとしても常時512EU/tを無意味に消費してしまいます。
それを防ぐため、必要なだけしか電力を使用しない調整エネルギーパイプ(Regulator Pipe)を作成できます。
レシピは木、石、金それぞれのエネルギーパイプ+電子回路。

エネルギーパイプと差し替えると、今度は機械の動作に必要な電力だけしか使用しなくなります。
なお変換効率は低めといいましたが、それでもクァーリーの動作に30EU/t程度しか使用しません。
全然低くないよな。
また、エネルギー連結器をクリックすることで、動作を逆にすることができます。
BCのエンジン動力をIC2のEUに変換することもできるわけです。
なのですが、一体誰がこの機能使うんでしょうかね。
ちなみに木エンジン1ストロークあたり2EUの出力です。
マインクラフトのまとめ
ということでEnergy Couplerは、ICの電力をBCのエンジン動力に変換することのできるMODです。
BCのエンジンは、エンジンごとに石炭やオイルの補充が必要なのがネックでしたが、これを使うとBCの機械をエンジンのかわりにEUで動かすことができるようになります。
これで発電機だけを管理すればよくなるため楽になりますね。
さらにソーラー発電機であれば一切の管理が不要になります。
なお、便利なだけあってエネルギー変換効率は低めに設定されています。
さっそく作ってみます。
低圧エネルギー連結器(LV Energy Coupler)はゴム*6、木エネルギーパイプ、充電池、銅ケーブル。
中圧エネルギー連結器(MV Energy Coupler)はゴム*6、木エネルギーパイプ、エナジークリスタル、金ケーブル。
高圧エネルギー連結器(HV Energy Coupler)はゴム*6、木エネルギーパイプ、ラポトロンクリスタル、精錬鉄ケーブル。
効果はまあ名前のとおりで、LVは最大32EU、MVは128EU、HVは512EUを入力し、対応するだけのBCのエネルギーを出力します。
エネルギー連結器のドット1つのほうにICの電力を、ドットが3つのほうにエネルギーパイプを接続し、その先をクァーリーなどBCのマシンに接続すると機械が動作します。
問題点としては、接続先にできるのは機械だけで、エンジンやパイプに対する動力源としては使用できません。
黒曜石パイプの回収範囲を広めるためにはこれまで通りエンジンを使用しなければならないようです。
もうひとつ欠点があり、通常のエネルギーパイプを使用すると常に全力でエネルギーを出力します。
高圧エネルギー連結器の先にエネルギー木パイプをつなげると、たとえその先に機械がなかったとしても常時512EU/tを無意味に消費してしまいます。
それを防ぐため、必要なだけしか電力を使用しない調整エネルギーパイプ(Regulator Pipe)を作成できます。
レシピは木、石、金それぞれのエネルギーパイプ+電子回路。
エネルギーパイプと差し替えると、今度は機械の動作に必要な電力だけしか使用しなくなります。
なお変換効率は低めといいましたが、それでもクァーリーの動作に30EU/t程度しか使用しません。
全然低くないよな。
また、エネルギー連結器をクリックすることで、動作を逆にすることができます。
BCのエンジン動力をIC2のEUに変換することもできるわけです。
なのですが、一体誰がこの機能使うんでしょうかね。
ちなみに木エンジン1ストロークあたり2EUの出力です。
マインクラフトのまとめ
IC2のバージョン1.0対応版1.42が公開されました。
はええ!予定より一週間早いよ!
ということで大急ぎでAdvanced Generatorsを紹介します。
Advanced Generatorsは、IC2にさらに色々な機械を追加するMODです。
執筆時のバージョンはpr5でした。
名前のとおりメインは発電機の上位機種なのですが、それ以外にも色々と追加要素があります。
今回は発電機の上位機種を紹介してみます。
まずは火力発電機の上位機種、高等火力発電機(Advanced Generator)。
レシピは火力発電機、リサイクル装置、アドバンスドマシン、合金板*4、銅ケーブル*2。

発電速度こそ5EU/tと元の火力発電機と変わりませんが、石炭での合計発電量は5000EUと2割アップしています。
そして最大の特徴は、発電していると30秒に1つスクラップを生成してくれるという点です。
メビウス燃料あたりを突っ込んでおくとスクラップが大漁なので、用途があれば物質製造器に、なければスクラップボックスにでもするとよいでしょう。
次は高等地熱発電機(Advanced GeoGenerator)。
レシピは地熱発電機、アドバンスドマシン、発展回路、強化ストーン*6。

溶岩バケツを突っ込むと、10EU/tで25000EUと、元の地熱発電機より2割増しで発電してくれます。
増幅率は高等火力発電機と同じです。
あと、何も素材を投入していない状態でも、何故か2秒に1EU程度の非常にゆっくりな速度でですが発電しました。
何故だろう。
次は高等ソーラー発電機(Advanced Solar Panel)。
前アドバンスドソーラーパネルを紹介しましたが、名前は同じでも完全に別物です。
レシピはソーラー発電機、地熱発電機、グラスファイバー*2、強化ガラス*2、金粉*3。
何故に地熱発電機?

効率は設置当初は1EUですが、パネルが暖まってくると徐々に発電量が増えていきます。
なんと最終的には5EUに!
あ、あれ、あんまりたいしたことがない。
なお、夜になるとパネルが冷えてしまいますが、Heater部分に充電池を置いておくと夜も暖かいままを保ってくれます。
なお、高等発電機全てに共通することですが、アドバンスドソーラーパネルのような蓄電機能はありません。

地熱とソーラーは単純な効率アップとして、火力はさらにスクラップの生成元として使うことができることでしょう。
さて、最後はAdvanced Generatorsオリジナルの発電機、空間エネルギー発電機(Void High-Energy Current Generator)。
レシピはMFSユニット、発展回路、ダイヤモンド、カーボンプレート*2、黒曜石*4。

非常に高コストですが、何が起きるかというと、何もない虚空からエネルギーを取り出してきます。
夢の無限エネルギー源です。
まあ、この世界では風力・水力・ソーラー発電機も無限エネルギー源ではありますが。
さて、こいつを設置すると、以後10秒に一回パルス波としてエネルギーが発生します。
地上で使用すると、なんと一回のパルスで5EUものエネルギーを発電します。
え?そんだけ?
なわけもなく、実は取り出せるエネルギー量は地下深くなるほど強くなります。
地底で使用すると、MFSユニットを吹き飛ばすほど強力なエネルギー源となります。
あと特徴として、エネルギーを取り出すたびに非常にやかましい爆発音がします。
うっかり生活空間の近くに置かないよう注意しましょう。
水力と風力は、何故か作成が大変なのでまた後日。
マインクラフトのまとめ
はええ!予定より一週間早いよ!
ということで大急ぎでAdvanced Generatorsを紹介します。
Advanced Generatorsは、IC2にさらに色々な機械を追加するMODです。
執筆時のバージョンはpr5でした。
名前のとおりメインは発電機の上位機種なのですが、それ以外にも色々と追加要素があります。
今回は発電機の上位機種を紹介してみます。
まずは火力発電機の上位機種、高等火力発電機(Advanced Generator)。
レシピは火力発電機、リサイクル装置、アドバンスドマシン、合金板*4、銅ケーブル*2。
発電速度こそ5EU/tと元の火力発電機と変わりませんが、石炭での合計発電量は5000EUと2割アップしています。
そして最大の特徴は、発電していると30秒に1つスクラップを生成してくれるという点です。
メビウス燃料あたりを突っ込んでおくとスクラップが大漁なので、用途があれば物質製造器に、なければスクラップボックスにでもするとよいでしょう。
次は高等地熱発電機(Advanced GeoGenerator)。
レシピは地熱発電機、アドバンスドマシン、発展回路、強化ストーン*6。
溶岩バケツを突っ込むと、10EU/tで25000EUと、元の地熱発電機より2割増しで発電してくれます。
増幅率は高等火力発電機と同じです。
あと、何も素材を投入していない状態でも、何故か2秒に1EU程度の非常にゆっくりな速度でですが発電しました。
何故だろう。
次は高等ソーラー発電機(Advanced Solar Panel)。
前アドバンスドソーラーパネルを紹介しましたが、名前は同じでも完全に別物です。
レシピはソーラー発電機、地熱発電機、グラスファイバー*2、強化ガラス*2、金粉*3。
何故に地熱発電機?
効率は設置当初は1EUですが、パネルが暖まってくると徐々に発電量が増えていきます。
なんと最終的には5EUに!
あ、あれ、あんまりたいしたことがない。
なお、夜になるとパネルが冷えてしまいますが、Heater部分に充電池を置いておくと夜も暖かいままを保ってくれます。
なお、高等発電機全てに共通することですが、アドバンスドソーラーパネルのような蓄電機能はありません。
地熱とソーラーは単純な効率アップとして、火力はさらにスクラップの生成元として使うことができることでしょう。
さて、最後はAdvanced Generatorsオリジナルの発電機、空間エネルギー発電機(Void High-Energy Current Generator)。
レシピはMFSユニット、発展回路、ダイヤモンド、カーボンプレート*2、黒曜石*4。
非常に高コストですが、何が起きるかというと、何もない虚空からエネルギーを取り出してきます。
夢の無限エネルギー源です。
まあ、この世界では風力・水力・ソーラー発電機も無限エネルギー源ではありますが。
さて、こいつを設置すると、以後10秒に一回パルス波としてエネルギーが発生します。
地上で使用すると、なんと一回のパルスで5EUものエネルギーを発電します。
え?そんだけ?
なわけもなく、実は取り出せるエネルギー量は地下深くなるほど強くなります。
地底で使用すると、MFSユニットを吹き飛ばすほど強力なエネルギー源となります。
あと特徴として、エネルギーを取り出すたびに非常にやかましい爆発音がします。
うっかり生活空間の近くに置かないよう注意しましょう。
水力と風力は、何故か作成が大変なのでまた後日。
マインクラフトのまとめ
リサイクル装置(Recycler)のレシピは圧縮機、土*3、精錬鉄*2、グロウストーンダスト。

リサイクル装置にゴミアイテムを突っ込むと、ゴミを処理しながら、希にスクラップ(Scrap)を生成してくれます。

64個のアイテムを突っ込んでできあがるスクラップは8個程度です。
できたスクラップを9個並べるとスクラップボックス(Scrap Box)ができます。

これを右クリックで使用すると、中からアイテムがランダムで出てきます。
とまあ、手動でどうこうするには非常に効率のよくないしろものです。
こんなのやってられませんので自動でやってしまいましょう。
BuildCraftのクァーリーで掘ったアイテムは、クァーリーの隣にチェストを置いておくとそちらに自動的に置かれます。
よって、そこから木パイプを繋いで中身を取り出します。

出力をダイヤモンドパイプで分岐させ、土や丸石といった不要物だけリサイクル装置に進むようにし、それ以外は回収用チェストに運びます。

写真では丸石をEEの分解レシピで土まで還元してからリサイクル装置に運搬するようにしていますが、正直さすがにそこまでしなくてもいいと思った。
出てきたスクラップは全自動作業台でスクラップボックスに変換し、回収用チェストに集めます。

これで不要物はスクラップボックスとなり、それ以外の鉱石などはそのまま回収用チェストに運ばれることとなります。
なお、リサイクル装置の処理速度より木エンジンの搬出速度の方が多少早いので、大量にアイテムがやってくると処理が間に合いません。
完璧を目指すならリサイクル装置の並列化が必要ですが、まあそこまでするほどの貴重品でもないのでこんなもので。
さて、こうやって完成したスクラップボックスを300ほど空けてみましたが、たいしたアイテムが出ません。
どうも全アイテムからではなく、一部のアイテムしか出現の候補にならないみたいです。
ブロック類はほとんど対象にならず、土や草、ネザーラックなどの一部しか出てきません。
アイテムもバニラとIC2のものしか対象にならないようで、他のMODのアイテムは出てきません。
さらにバニラやIC2でも全アイテムが出るかというとそういうことはなく、金のヘルメットはやたらいっぱい出るのに他の部位は出ず、他素材の武器防具も全く出ない、使い捨て電池(Single Use Battery)は出るけど充電式電池(RE Battery)は出ないというふうに取得制限がかかっているようです。
出るアイテムもせいぜい鉱石レベル、希にダイヤモンドというレベルで、クアンタムアーマーはおろかゴムブーツすら出る気配がありません。
正直これだけ設備投資する価値があるかどうかかなり微妙。
スクラップを物質製造器に突っ込むと、マターの生成速度が少し速くなるので、マターを使う宛があればそっちに注ぎ込んだ方がいいかもしれません。
マインクラフトのまとめ
リサイクル装置にゴミアイテムを突っ込むと、ゴミを処理しながら、希にスクラップ(Scrap)を生成してくれます。
64個のアイテムを突っ込んでできあがるスクラップは8個程度です。
できたスクラップを9個並べるとスクラップボックス(Scrap Box)ができます。
これを右クリックで使用すると、中からアイテムがランダムで出てきます。
とまあ、手動でどうこうするには非常に効率のよくないしろものです。
こんなのやってられませんので自動でやってしまいましょう。
BuildCraftのクァーリーで掘ったアイテムは、クァーリーの隣にチェストを置いておくとそちらに自動的に置かれます。
よって、そこから木パイプを繋いで中身を取り出します。
出力をダイヤモンドパイプで分岐させ、土や丸石といった不要物だけリサイクル装置に進むようにし、それ以外は回収用チェストに運びます。
写真では丸石をEEの分解レシピで土まで還元してからリサイクル装置に運搬するようにしていますが、正直さすがにそこまでしなくてもいいと思った。
出てきたスクラップは全自動作業台でスクラップボックスに変換し、回収用チェストに集めます。
これで不要物はスクラップボックスとなり、それ以外の鉱石などはそのまま回収用チェストに運ばれることとなります。
なお、リサイクル装置の処理速度より木エンジンの搬出速度の方が多少早いので、大量にアイテムがやってくると処理が間に合いません。
完璧を目指すならリサイクル装置の並列化が必要ですが、まあそこまでするほどの貴重品でもないのでこんなもので。
さて、こうやって完成したスクラップボックスを300ほど空けてみましたが、たいしたアイテムが出ません。
どうも全アイテムからではなく、一部のアイテムしか出現の候補にならないみたいです。
ブロック類はほとんど対象にならず、土や草、ネザーラックなどの一部しか出てきません。
アイテムもバニラとIC2のものしか対象にならないようで、他のMODのアイテムは出てきません。
さらにバニラやIC2でも全アイテムが出るかというとそういうことはなく、金のヘルメットはやたらいっぱい出るのに他の部位は出ず、他素材の武器防具も全く出ない、使い捨て電池(Single Use Battery)は出るけど充電式電池(RE Battery)は出ないというふうに取得制限がかかっているようです。
出るアイテムもせいぜい鉱石レベル、希にダイヤモンドというレベルで、クアンタムアーマーはおろかゴムブーツすら出る気配がありません。
正直これだけ設備投資する価値があるかどうかかなり微妙。
スクラップを物質製造器に突っ込むと、マターの生成速度が少し速くなるので、マターを使う宛があればそっちに注ぎ込んだ方がいいかもしれません。
マインクラフトのまとめ
前回「最初から用意しろよ」とか言いましたが、実はZend_Applicationで実現できます。
クイックスタートを利用して前回までのZend_Controllerを書き換えてみます。
クイックスタートは2種類ありますが、Zend_Toolを利用する方法は新規プロジェクト用なので後者を使用します。
まずBootstrapを作成。
application/Bootstrap.php
html/index.php
順番に見ていきましょう。
Bootstrap.phpは、毎回必ず呼ばれるクラスになります。
前回作ったBaseController.phpのようなものですが、予めシステムに組み込まれているぶんrequire_onceを書いたりextendsしたりしなくてすむようになります。
これ一体何処からどうやって呼ばれているのかさっぱりわからない。
application.iniは設定ファイルです。
書き方はZend_Configの記事を参照してください。
'production'、'staging'、'testing'、'development'の4環境を設置しています。
まあ大抵は'production''development'の二つしか使いませんが。
public/index.phpはインデックスです。
BaseControllerではrun()するだけでしたが、Zend_Applicationは幾つか事前準備が必要です。
定数APPLICATION_ENVはapplication.iniに対するどの環境かを設定しています。
定数APPLICATION_ENVの中身は環境変数APPLICATION_ENVから取得しており、その環境変数APPLICATION_ENVはhtml/.htaccessで'development'と指定しているので開発環境となります。
従って本番環境ではhtml/.htaccessの中身が'production'となります。
これでとりあえず準備ができたのでブラウザで実行。
Warning: require_once(APP_DIRcontrollers/BaseController.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\hoge\fuga\application\controllers\IndexController.php on line 3
お?
クイックスタートを利用して前回までのZend_Controllerを書き換えてみます。
クイックスタートは2種類ありますが、Zend_Toolを利用する方法は新規プロジェクト用なので後者を使用します。
まずBootstrapを作成。
application/Bootstrap.php
<?php
class Bootstrap extends Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap{}
コンフィグファイルを作成。
[production] phpSettings.display_startup_errors = 0 phpSettings.display_errors = 0 includePaths.library = APPLICATION_PATH "/../library" bootstrap.path = APPLICATION_PATH "/Bootstrap.php" bootstrap.class = "Bootstrap" resources.frontController.controllerDirectory = APPLICATION_PATH "/controllers" [staging : production] [testing : production] phpSettings.display_startup_errors = 1 phpSettings.display_errors = 1 [development : production] phpSettings.display_startup_errors = 1 phpSettings.display_errors = 1インデックスを書き換え。
html/index.php
<?php
// アプリケーション・ディレクトリへのパスを定義します
defined('APPLICATION_PATH')
|| define('APPLICATION_PATH',
realpath(dirname(__FILE__) . '/../application'));
// アプリケーション環境
defined('APPLICATION_ENV')
|| define('APPLICATION_ENV',
(getenv('APPLICATION_ENV') ? getenv('APPLICATION_ENV')
: 'production'));
// 必要があればinclude_pathを追加
set_include_path(implode(PATH_SEPARATOR, array(
dirname(dirname(__FILE__)) . '/library',
get_include_path(),
)));
// Zend_Applicationを実行
require_once 'Zend/Application.php';
$application = new Zend_Application(
APPLICATION_ENV,
APPLICATION_PATH . '/configs/application.ini'
);
$application->bootstrap()
->run();
html/.htaccessに一行追加。
SetEnv APPLICATION_ENV developmentほとんどコピペしただけです。
順番に見ていきましょう。
Bootstrap.phpは、毎回必ず呼ばれるクラスになります。
前回作ったBaseController.phpのようなものですが、予めシステムに組み込まれているぶんrequire_onceを書いたりextendsしたりしなくてすむようになります。
これ一体何処からどうやって呼ばれているのかさっぱりわからない。
application.iniは設定ファイルです。
書き方はZend_Configの記事を参照してください。
'production'、'staging'、'testing'、'development'の4環境を設置しています。
まあ大抵は'production''development'の二つしか使いませんが。
public/index.phpはインデックスです。
BaseControllerではrun()するだけでしたが、Zend_Applicationは幾つか事前準備が必要です。
定数APPLICATION_ENVはapplication.iniに対するどの環境かを設定しています。
定数APPLICATION_ENVの中身は環境変数APPLICATION_ENVから取得しており、その環境変数APPLICATION_ENVはhtml/.htaccessで'development'と指定しているので開発環境となります。
従って本番環境ではhtml/.htaccessの中身が'production'となります。
これでとりあえず準備ができたのでブラウザで実行。
Warning: require_once(APP_DIRcontrollers/BaseController.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\hoge\fuga\application\controllers\IndexController.php on line 3
お?
The Elder Scrolls V : Skyrim
スカイリムようやく見つけました。
とりあえず一匹目のドラゴンまで撃破したところ。
最初の洞窟を抜けたときにオブリほどの感銘を受けなかったんだけど、やはり色彩豊かな平原じゃなくてモノトーンの山岳だったせいですかね。
どうも雪が多くて、全体的にオブリに比べて白黒成分が多くて鮮やかな感じがしないのがちょっと残念。
もっと歩けば明るいところも出てくるんだよな?
ぶたボット1 5月病マリオ
☆☆☆
ニコニコ静画でやっているぶたボットのコミックです。
といっても静画をそのまま載せただけなので、実はあえて買う必要は全くなかったりします。
まあそれでも買ってしまうのが本読みのサガ。
なお、一巻には第一話~第六話までが収録されています。
既存だけでも8巻近くあるのかよ。
漫画形式の情報量の少なさに改めてびっくりです。
生徒会役員共5 氏家 ト全
生徒会役員共6
☆☆☆
あーうん、この作者だなあ。
昔から何も変わらず進展もないぐるぐるまんがです。
いっそのこと一巻全部スズでひとつ。
情報処理教科書 エンベデッドシステムスペシャリスト 2012年版
春はプロジェクトマネージャとシステム監査とエンベデッドが残っていて、ではこの中でどれを選ぶかって言われたらこれしかなくないか?
これまでの分野とだいぶかけ離れているので、かなり苦戦しそうな気がします。
論理回路とか実はさっぱりわからないのでレッドストーン回路で勉強するよ!
