久々に実績取った。
迷宮クロスブラッド、システムがよくわかんない。
とりあえずサブディスクからアイテムの取り出し方がわからん。
ベントー5 北海道産炭火焼き秋鮭弁当285円 アサウラ
ベントー5.5 箸休め~燃えよ狼
ベントー6 和栗おこわ弁当310円
ベントー7 真・和風ロールキャベツ弁当280円
ベントー7.5 箸休め Wolves, be ambitious!
☆☆☆☆☆
半額弁当を奪い合ってガチバトル。
何言ってるのかわからない?
大丈夫。私にはわかる。
そしてあなたもこれを読めばわかる。
傍目には超くだらないことを大まじめにやっちゃう馬鹿さ極まれる名作。
時折妄想がぶっとんでいって読みづらくなることがあるのでそこさえどうにかなればなあ。
あとひとつだけ真面目にアドバイスすると、電車への駆け込み乗車は危険なのでおやめください。
てかマジ迷惑なのでやめろ。
迷宮クロスブラッド、システムがよくわかんない。
とりあえずサブディスクからアイテムの取り出し方がわからん。
ベントー5 北海道産炭火焼き秋鮭弁当285円 アサウラ
ベントー5.5 箸休め~燃えよ狼
ベントー6 和栗おこわ弁当310円
ベントー7 真・和風ロールキャベツ弁当280円
ベントー7.5 箸休め Wolves, be ambitious!
☆☆☆☆☆
半額弁当を奪い合ってガチバトル。
何言ってるのかわからない?
大丈夫。私にはわかる。
そしてあなたもこれを読めばわかる。
傍目には超くだらないことを大まじめにやっちゃう馬鹿さ極まれる名作。
時折妄想がぶっとんでいって読みづらくなることがあるのでそこさえどうにかなればなあ。
あとひとつだけ真面目にアドバイスすると、電車への駆け込み乗車は危険なのでおやめください。
てかマジ迷惑なのでやめろ。
PR
正式版1.0がリリースされましたが、主要MODが対応するまではしばらくこのままで行こうと思います。
IndustrialCraft2には火力・地熱・水力・風力・ソーラー・原子力発電機があります。
このうち水力は発電量が低すぎるため使い物になりません。
原子力発電機は超高性能ですが、必要な工数が非常に多いうえ運用を誤ると爆発したりして大変みたいです。
火力・地熱は定期的に燃料補給が必要なため、最終的には運用から外したいところです。
ということで残るは風力とソーラーですが、今回はソーラー発電機を作ってみます。
ソーラー発電機の制限は、真上に不透明なブロックがないこと、そして昼間しか発電できないことです。
出力は1EUで、粉砕器ひとつ動かすにも2機が必要になります。
上記特性を考えると、ソーラー発電機は大量に作った上で蓄電器に電力をまとめるという運用が最適と言えます。
なにより一度作ってしまえば補給いらずというのが素晴らしい点です。
ソーラー発電機のレシピは、火力発電機*1+銅ケーブル*2+石炭の粉*3+ガラス*3となります。

さっそくセットしていきますが、配置には少々こつが要ります。
ポイントは蓄電器の向き。
花形にセットしていくのですが、まず一番中央になる予定のところに仮ブロックを置きます。

その仮ブロックの下に、上を向きながらバットボックスを設置します。

そうしたら仮ブロックを排除し、ソーラー発電機をひとつ設置します。
ソーラー発電機は発電機構が常時上を向くため、下から設置してもかまいません。

その後バットボックスの四方を囲むようにソーラー発電機を4つ設置します。
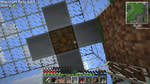
これでソーラー発電機の花が完成です。
下以外の5面にくっついているソーラーパネルの出力をバットボックスが集約し、下向きに出力するという無駄のない構造になりました。

このソーラー発電機は、昼であれば花ひとつあたり5EUを出力することができます。
火力発電機5機を使ってようやく火力発電機一機と同じ出力といわれればたいしたことがないようにも聞こえますが、一度設置さえしてしまえば以後燃料を一切使う必要がないというのが最大の特徴です。
IndustrialCraft2には火力・地熱・水力・風力・ソーラー・原子力発電機があります。
このうち水力は発電量が低すぎるため使い物になりません。
原子力発電機は超高性能ですが、必要な工数が非常に多いうえ運用を誤ると爆発したりして大変みたいです。
火力・地熱は定期的に燃料補給が必要なため、最終的には運用から外したいところです。
ということで残るは風力とソーラーですが、今回はソーラー発電機を作ってみます。
ソーラー発電機の制限は、真上に不透明なブロックがないこと、そして昼間しか発電できないことです。
出力は1EUで、粉砕器ひとつ動かすにも2機が必要になります。
上記特性を考えると、ソーラー発電機は大量に作った上で蓄電器に電力をまとめるという運用が最適と言えます。
なにより一度作ってしまえば補給いらずというのが素晴らしい点です。
ソーラー発電機のレシピは、火力発電機*1+銅ケーブル*2+石炭の粉*3+ガラス*3となります。
さっそくセットしていきますが、配置には少々こつが要ります。
ポイントは蓄電器の向き。
花形にセットしていくのですが、まず一番中央になる予定のところに仮ブロックを置きます。
その仮ブロックの下に、上を向きながらバットボックスを設置します。
そうしたら仮ブロックを排除し、ソーラー発電機をひとつ設置します。
ソーラー発電機は発電機構が常時上を向くため、下から設置してもかまいません。
その後バットボックスの四方を囲むようにソーラー発電機を4つ設置します。
これでソーラー発電機の花が完成です。
下以外の5面にくっついているソーラーパネルの出力をバットボックスが集約し、下向きに出力するという無駄のない構造になりました。
このソーラー発電機は、昼であれば花ひとつあたり5EUを出力することができます。
火力発電機5機を使ってようやく火力発電機一機と同じ出力といわれればたいしたことがないようにも聞こえますが、一度設置さえしてしまえば以後燃料を一切使う必要がないというのが最大の特徴です。
とりあえず前回の解説から。
最後に開いたURLはhttp://zend.localhost/index/indexでした。
最初のindexはindexコントローラを呼び出すという意味で、後ろのindexはコントローラ内のindexアクションを呼び出すという意味です。
結果としてIndexController.php内のIndexController::indexAction()が呼び出されます。
同様に例えばhttp://zend.localhost/hoge/fugaだったら、HogeController.php内のHogeController::fugaAction()が呼び出されるということになります。
http://zend.localhost/だけでもHello, World!が表示されますが、これはコントローラ名やアクション名が省かれた場合はindexとして扱われるためです。
http://framework.zend.com/manual/1.11/ja/zend.controller.quickstart.html#zend.controller.quickstart.go.controller
特に指定しないかぎりビューについてもファイルが自動的に決定され、application/views/scripts/コントローラ名/アクション名.phtmlになります。
URLがhttp://zend.localhost/hoge/fugaであればapplication/views/scripts/hoge/fuga.phtmlです。
そのscriptsってなんだよ。
さて、試しにhttp://zend.localhost/index/aってするとFatal errorが発生します。
IndexController::aAction()が存在しないためです。
このようなエラーをまとめて捕捉できる仕組みが用意されており、エラーコントローラと呼ばれています。
application/controllers/ErrorController.php
現在はただのダミーですが、errorAction()内で原因を取得したりといったこともできます。
ただこれを実装すると、うっかり例外が出てしまったときにエラーコントローラに奪われてしまってvar_dump()などが効かなくなるので、開発時はオフにしておきましょう。
その後はフロントコントローラとか標準のルータとかが色々書いてあるんだけど何に使うのかよくわからんのでとりあえずスルー。
リクエストオブジェクトだけは大事なのでやっておきます。
といってもまあ単に$_REQUESTを取得するってだけですが。
http://zend.localhost/index/index/?a=b&c=d
http://zend.localhost/index/index/a/b/c/d
両方とも同じ意味になり、indexコントローラのindexアクションを呼び、リクエストパラメータaの値が'b'、cの値が'd'という呼び出しになります。
Zend_Controller_Action::getRequest()でリクエストオブジェクトを取得でき、リクエストオブジェクトを通じてコントローラ名やアクション名、リクエストパラメータなどにアクセスできます。
この場合はコントローラ名は'index'、アクション名も'index'になります。
また、コントローラよりさらに大きい単位でモジュールという区分けができるのですが、そこは触っていないのでデフォルトの'default'になります。
IndexController::indexAction()内で実行したところで全く意味のないメソッドですが、そのうち役に立つことが出てくるでしょう、たぶん。
重要なのが最後のgetParam()とgetParams()です。
getParam('a')でリクエストパラメータaの中身、即ち'b'が取得できます。
getParams()は全てのリクエストパラメータを配列で取得します。
他にもリクエストメソッドとかisXmlHttpRequest()とかあるみたいですが、まだ使わないのでパス。
ディスパッチもちょっとだけ。
_forward()メソッドで別のコントローラ、アクションを実行しなおすことができます。
http://zend.localhost/index/hoge/を指定したかのようにhogeActionが実行されapplication/views/scripts/index/hoge.phtmlが表示されます。
ただしリクエストオブジェクトの中身は'index'コントローラ、'index'アクションのままで変更されず、リクエストパラメータもそのまま引き継がれます。
入力確認画面で入力チェックに引っかかったら入力画面に戻す、といった使い方になるのでしょう。
最後に開いたURLはhttp://zend.localhost/index/indexでした。
最初のindexはindexコントローラを呼び出すという意味で、後ろのindexはコントローラ内のindexアクションを呼び出すという意味です。
結果としてIndexController.php内のIndexController::indexAction()が呼び出されます。
同様に例えばhttp://zend.localhost/hoge/fugaだったら、HogeController.php内のHogeController::fugaAction()が呼び出されるということになります。
http://zend.localhost/だけでもHello, World!が表示されますが、これはコントローラ名やアクション名が省かれた場合はindexとして扱われるためです。
http://framework.zend.com/manual/1.11/ja/zend.controller.quickstart.html#zend.controller.quickstart.go.controller
特に指定しないかぎりビューについてもファイルが自動的に決定され、application/views/scripts/コントローラ名/アクション名.phtmlになります。
URLがhttp://zend.localhost/hoge/fugaであればapplication/views/scripts/hoge/fuga.phtmlです。
そのscriptsってなんだよ。
さて、試しにhttp://zend.localhost/index/aってするとFatal errorが発生します。
IndexController::aAction()が存在しないためです。
このようなエラーをまとめて捕捉できる仕組みが用意されており、エラーコントローラと呼ばれています。
application/controllers/ErrorController.php
<?php
class ErrorController extends Zend_Controller_Action{
public function errorAction(){}
}
application/views/scripts/error/error.phtml<html><body>なんかエラー</body></html>例外が発生するとErrorController::errorAction()が呼ばれ、error/error.phtmlが表示されます。
現在はただのダミーですが、errorAction()内で原因を取得したりといったこともできます。
ただこれを実装すると、うっかり例外が出てしまったときにエラーコントローラに奪われてしまってvar_dump()などが効かなくなるので、開発時はオフにしておきましょう。
その後はフロントコントローラとか標準のルータとかが色々書いてあるんだけど何に使うのかよくわからんのでとりあえずスルー。
リクエストオブジェクトだけは大事なのでやっておきます。
といってもまあ単に$_REQUESTを取得するってだけですが。
class IndexController extends Zend_Controller_Action
{
public function indexAction()
{
$request = $this->getRequest();
$moduleName = $request->getModuleName();
$controllerName = $request->getControllerName();
$actionName = $request->getActionName();
$params = $request->getParams();
$request['a'] = $request->getParam('a');
}
}
適当にリクエストパラメータ付きでURLを呼び出してみます。http://zend.localhost/index/index/?a=b&c=d
http://zend.localhost/index/index/a/b/c/d
両方とも同じ意味になり、indexコントローラのindexアクションを呼び、リクエストパラメータaの値が'b'、cの値が'd'という呼び出しになります。
Zend_Controller_Action::getRequest()でリクエストオブジェクトを取得でき、リクエストオブジェクトを通じてコントローラ名やアクション名、リクエストパラメータなどにアクセスできます。
この場合はコントローラ名は'index'、アクション名も'index'になります。
また、コントローラよりさらに大きい単位でモジュールという区分けができるのですが、そこは触っていないのでデフォルトの'default'になります。
IndexController::indexAction()内で実行したところで全く意味のないメソッドですが、そのうち役に立つことが出てくるでしょう、たぶん。
重要なのが最後のgetParam()とgetParams()です。
getParam('a')でリクエストパラメータaの中身、即ち'b'が取得できます。
getParams()は全てのリクエストパラメータを配列で取得します。
他にもリクエストメソッドとかisXmlHttpRequest()とかあるみたいですが、まだ使わないのでパス。
ディスパッチもちょっとだけ。
_forward()メソッドで別のコントローラ、アクションを実行しなおすことができます。
<?php
class IndexController extends Zend_Controller_Action{
public function indexAction(){
$this->_forward('hoge', null, null, array('e'=>'f'));
}
public function hogeAction(){
var_dump($this->getRequest()->getParams());
}
}
http://zend.localhost/index/hoge/を指定したかのようにhogeActionが実行されapplication/views/scripts/index/hoge.phtmlが表示されます。
ただしリクエストオブジェクトの中身は'index'コントローラ、'index'アクションのままで変更されず、リクエストパラメータもそのまま引き継がれます。
入力確認画面で入力チェックに引っかかったら入力画面に戻す、といった使い方になるのでしょう。
火力発電機に燃料を入れると、燃料は全部燃えて電力になります。
隣で粉砕器が稼働していればそちらで消費されますが、何も機械が動いていない場合、せっかく作られた電力が無駄に捨てられてしまいます。
そこで蓄電器を作りましょう。
蓄電器は、発電機からの電力を消費せずに貯めておき、電気を使う段になって必要なだけ使ってくれるという優れものです。
蓄電器にも種類がありますが、まずは一番簡単なバットボックス。
簡単だけあって性能も低いのですが、作成も低コストで行えるのでまずこれを目指します。
素材は木材*5+充電式電池*3+銅ケーブル。

あとレンチも作っておきます。
向きのある機械に向かって使うと方向を変更でき、また自分の方を向いた状態で再度使用すると撤去することができます。
ただしレンチを使っても時折機械が壊れてしまい、マシンボックスになってしまうことがあります。
粉砕器で粉砕した銅とスズの粉を3:1で混ぜると青銅の粉(Bronze Dust)ができあがります。

青銅の粉を精錬すると青銅(Bronze)ができます。
正直銅と見分けが付きにくいです。
完成した青銅は、基本的に鉄のかわりとしてツールや防具に使用するとよいですが、6個使用するとレンチ(Wrench)が作成できます。
右クリック一発で機械が撤去できる優れものですが、希に失敗するのは前述の通り。

完成したバットボックスを、火力発電機と粉砕器の間に設置します。

目の前の木の箱みたいなのがバットボックスです。
設置したときに手前の一面にだけぽっちある面ができ、その面からのみEUを出力します。
それ以外の5面からはEUを吸収します。
つまりこの画面の通りに作ると、粉砕器からEUを吸収し手前に向かって放出するという動作になるので粉砕器が動作しません。
蓄電器の向きには注意しましょう。
この場合、粉砕器の方に移動し、粉砕器の向こうからバットボックスに向かってレンチを使用すると正しい向きに向け直すことができます。
最後に火力発電機に燃料を入れると、EUがバットボックスに蓄電されるようになります。

バットボックスの蓄電容量は40000EU、出力は32EUです。
石炭1個あたりの出力は4000EUなので、石炭10個燃やした分の電力を貯めておくことができます。
その後粉砕器にアイテムを投入すると、バットボックスに貯められた電力を使って動作します。
また、バットボックスのアイテム欄に充電式電池などの充電式アイテムを置くと充電することも可能ですが、そこらへんはまたそのうち。
隣で粉砕器が稼働していればそちらで消費されますが、何も機械が動いていない場合、せっかく作られた電力が無駄に捨てられてしまいます。
そこで蓄電器を作りましょう。
蓄電器は、発電機からの電力を消費せずに貯めておき、電気を使う段になって必要なだけ使ってくれるという優れものです。
蓄電器にも種類がありますが、まずは一番簡単なバットボックス。
簡単だけあって性能も低いのですが、作成も低コストで行えるのでまずこれを目指します。
素材は木材*5+充電式電池*3+銅ケーブル。
あとレンチも作っておきます。
向きのある機械に向かって使うと方向を変更でき、また自分の方を向いた状態で再度使用すると撤去することができます。
ただしレンチを使っても時折機械が壊れてしまい、マシンボックスになってしまうことがあります。
粉砕器で粉砕した銅とスズの粉を3:1で混ぜると青銅の粉(Bronze Dust)ができあがります。
青銅の粉を精錬すると青銅(Bronze)ができます。
正直銅と見分けが付きにくいです。
完成した青銅は、基本的に鉄のかわりとしてツールや防具に使用するとよいですが、6個使用するとレンチ(Wrench)が作成できます。
右クリック一発で機械が撤去できる優れものですが、希に失敗するのは前述の通り。
完成したバットボックスを、火力発電機と粉砕器の間に設置します。
目の前の木の箱みたいなのがバットボックスです。
設置したときに手前の一面にだけぽっちある面ができ、その面からのみEUを出力します。
それ以外の5面からはEUを吸収します。
つまりこの画面の通りに作ると、粉砕器からEUを吸収し手前に向かって放出するという動作になるので粉砕器が動作しません。
蓄電器の向きには注意しましょう。
この場合、粉砕器の方に移動し、粉砕器の向こうからバットボックスに向かってレンチを使用すると正しい向きに向け直すことができます。
最後に火力発電機に燃料を入れると、EUがバットボックスに蓄電されるようになります。
バットボックスの蓄電容量は40000EU、出力は32EUです。
石炭1個あたりの出力は4000EUなので、石炭10個燃やした分の電力を貯めておくことができます。
その後粉砕器にアイテムを投入すると、バットボックスに貯められた電力を使って動作します。
また、バットボックスのアイテム欄に充電式電池などの充電式アイテムを置くと充電することも可能ですが、そこらへんはまたそのうち。
前回発電機を作りました。
せっかく発電機を作ったのだから、次は電気を使う機械を作ってみます。
機械にも色々ありますが、まずは一番便利な粉砕器を作ります。
粉砕器は鉄鉱石などの鉱石を粉(Dusts)*2にしてくれます。
粉1つを精製するとインゴット1つになります。
つまり、粉砕器を経由するとインゴットが何故か二倍に。
先に必要な部品である電子回路(Electronic Circuit)を作成。
この電子回路もちょくちょく使うことになります。
素材は銅ケーブル*6、レッドストーン*2、鋼鉄。

次にいよいよ粉砕器(Mecerator)を作成。
素材はフリント*3、丸石*2、マシンブロック、電子回路。

完成したら火力発電機と粉砕器を隣り合わせて設置。

粉砕器の上スロットに原料の鉱石を入れ、火力発電機の下スロットに石炭などの燃料を入れると、騒音を立てて粉砕器が始動します。


無事に粉砕されました。
鉱石を6個しか使っていないのに粉末が12個できています。
これを焼き固めるとインゴットが12個できあがります。
めでたし。
せっかく発電機を作ったのだから、次は電気を使う機械を作ってみます。
機械にも色々ありますが、まずは一番便利な粉砕器を作ります。
粉砕器は鉄鉱石などの鉱石を粉(Dusts)*2にしてくれます。
粉1つを精製するとインゴット1つになります。
つまり、粉砕器を経由するとインゴットが何故か二倍に。
先に必要な部品である電子回路(Electronic Circuit)を作成。
この電子回路もちょくちょく使うことになります。
素材は銅ケーブル*6、レッドストーン*2、鋼鉄。
次にいよいよ粉砕器(Mecerator)を作成。
素材はフリント*3、丸石*2、マシンブロック、電子回路。
完成したら火力発電機と粉砕器を隣り合わせて設置。
粉砕器の上スロットに原料の鉱石を入れ、火力発電機の下スロットに石炭などの燃料を入れると、騒音を立てて粉砕器が始動します。
無事に粉砕されました。
鉱石を6個しか使っていないのに粉末が12個できています。
これを焼き固めるとインゴットが12個できあがります。
めでたし。
IC2はマインクラフトに科学的・工業的要素を追加するMODです。
http://www26.atwiki.jp/minecraft/pages/322.html
http://www26.atwiki.jp/minecraft/pages/324.html
Wikiのページを見ればアイテムとかのリストはあるのですが、では実際どうしたらいいのかというあたりがいまいちよくわかりません。
とりあえず手を出してみましょう。
新要素をざっと見ると、ゴムから始まる配線系、鋼鉄から始まる機械系、石炭の粉から始まる素材系、鉄の代わりになる青銅などがあります。
まず青銅については、IC2が鉄を多く消費するためにその代替として作られた救済措置のようです。
スズ(Tin)と銅(Copper)から作りますが、使えるようになる前に発電機が必要なので解説も後回しにします。
石炭の粉も使用するのは後なので後回し。
どうでもいいけどRedPowerを一緒に入れると、同じ見た目で同じ名前だけど互換性のないスズと銅ができるのでものすごくわかりにくいです。
最新版では互換できるようになるみたいですが、今手元に入っているバージョンではできませんでした。
さて、まずはおまけレシピですが、かまどのアップグレード版である鉄のかまどを作ります。
レシピはかまど + 鉄*5。

電気が不要で、通常のかまどの1.25倍の性能になります。
IC2の機能を全く使用しないので、とりあえず通常のかまどを置き換えてしまって問題ありません。
さて、ここからは電力を扱っていきます。
IC2の基本は電力……ではなくゴムです。
ゴムがなければとりあえずなにもできません。
まずはゴムの取得に必要となるTreetapを作成。
レシピは木材*5。

何個か持ったらゴムの木を探しに行きます。
通常の木に混ざって、幹が黒くて葉の色が少しくすんでいるのがゴムの木です。
特に低湿地でよく見つかるみたい。
前、近くに低湿地があった方がいいと言っていたのはこのためです。

表札みたいなものが樹液溜まりで、そこに向かってTreetapを使うと樹液(Sticky Resin)を獲得できます。
樹液をかまどで精錬するとゴムができあがります。
ゴム*6と銅インゴット*3で銅のケーブル(Copper Cable)を作成できます。

ケーブルには他にも種類があって、高電圧に耐えられる鋼鉄ケーブルやグラスファイバーなどがありますが、とりあえずは銅ケーブルで十分です。
銅ケーブルの耐圧性能は32EUです。
このEUというのはIC2の電力の単位で、1tickあたりの電力量を示しています。
tickはまあフレームと思っておけばいいです(正確には1/20秒)
詳細な出力などはWikiのリストに掲載されていますが、火力発電機は5EU/tickを生産、電気炉は3EU/tickを消費、といった具合で管理されています。
銅ケーブルは32EUまでの電力を流すことができるので、電気炉を10個まで安定稼働させることができます。
なお銅ケーブルは電気を流す以外にも、多くの部品の材料になるため、今後大量に必要となります。
さて次はメインである火力発電機(Generator)を作ります。
火力発電機はそれ自体が発電機となるのはもちろん、他の発電機を作るのにも何故か必要となる重要なアイテムです。
材料として必要になる鋼鉄から始めます。
鋼鉄の作り方は非常に簡単。
鉄をかまどでもう一度焼くだけです。
次に鋼鉄*8を合成するとマシンブロック(Machine Block)ができます。

マシンブロックは、今後機械装置を作るためによく必要となる部品です。
次は充電式電池(RE-Battery)を製作。
素材はスズ*4、レッドストーン*2、銅ケーブル。

鋼鉄と充電式電池でさっそく火力発電機を作成。
レシピは充電式電池+鋼鉄+鉄のかまど。

これで火力発電機が完成しました。
火力発電機は石炭などを燃やして電力に変換する機能を持っています。
出力は5EU/tickで、石炭であれば合計4000EUを発電します。
次回は電力を使う機械を作ってみましょう。
http://www26.atwiki.jp/minecraft/pages/322.html
http://www26.atwiki.jp/minecraft/pages/324.html
Wikiのページを見ればアイテムとかのリストはあるのですが、では実際どうしたらいいのかというあたりがいまいちよくわかりません。
とりあえず手を出してみましょう。
新要素をざっと見ると、ゴムから始まる配線系、鋼鉄から始まる機械系、石炭の粉から始まる素材系、鉄の代わりになる青銅などがあります。
まず青銅については、IC2が鉄を多く消費するためにその代替として作られた救済措置のようです。
スズ(Tin)と銅(Copper)から作りますが、使えるようになる前に発電機が必要なので解説も後回しにします。
石炭の粉も使用するのは後なので後回し。
どうでもいいけどRedPowerを一緒に入れると、同じ見た目で同じ名前だけど互換性のないスズと銅ができるのでものすごくわかりにくいです。
最新版では互換できるようになるみたいですが、今手元に入っているバージョンではできませんでした。
さて、まずはおまけレシピですが、かまどのアップグレード版である鉄のかまどを作ります。
レシピはかまど + 鉄*5。
電気が不要で、通常のかまどの1.25倍の性能になります。
IC2の機能を全く使用しないので、とりあえず通常のかまどを置き換えてしまって問題ありません。
さて、ここからは電力を扱っていきます。
IC2の基本は電力……ではなくゴムです。
ゴムがなければとりあえずなにもできません。
まずはゴムの取得に必要となるTreetapを作成。
レシピは木材*5。
何個か持ったらゴムの木を探しに行きます。
通常の木に混ざって、幹が黒くて葉の色が少しくすんでいるのがゴムの木です。
特に低湿地でよく見つかるみたい。
前、近くに低湿地があった方がいいと言っていたのはこのためです。
表札みたいなものが樹液溜まりで、そこに向かってTreetapを使うと樹液(Sticky Resin)を獲得できます。
樹液をかまどで精錬するとゴムができあがります。
ゴム*6と銅インゴット*3で銅のケーブル(Copper Cable)を作成できます。
ケーブルには他にも種類があって、高電圧に耐えられる鋼鉄ケーブルやグラスファイバーなどがありますが、とりあえずは銅ケーブルで十分です。
銅ケーブルの耐圧性能は32EUです。
このEUというのはIC2の電力の単位で、1tickあたりの電力量を示しています。
tickはまあフレームと思っておけばいいです(正確には1/20秒)
詳細な出力などはWikiのリストに掲載されていますが、火力発電機は5EU/tickを生産、電気炉は3EU/tickを消費、といった具合で管理されています。
銅ケーブルは32EUまでの電力を流すことができるので、電気炉を10個まで安定稼働させることができます。
なお銅ケーブルは電気を流す以外にも、多くの部品の材料になるため、今後大量に必要となります。
さて次はメインである火力発電機(Generator)を作ります。
火力発電機はそれ自体が発電機となるのはもちろん、他の発電機を作るのにも何故か必要となる重要なアイテムです。
材料として必要になる鋼鉄から始めます。
鋼鉄の作り方は非常に簡単。
鉄をかまどでもう一度焼くだけです。
次に鋼鉄*8を合成するとマシンブロック(Machine Block)ができます。
マシンブロックは、今後機械装置を作るためによく必要となる部品です。
次は充電式電池(RE-Battery)を製作。
素材はスズ*4、レッドストーン*2、銅ケーブル。
鋼鉄と充電式電池でさっそく火力発電機を作成。
レシピは充電式電池+鋼鉄+鉄のかまど。
これで火力発電機が完成しました。
火力発電機は石炭などを燃やして電力に変換する機能を持っています。
出力は5EU/tickで、石炭であれば合計4000EUを発電します。
次回は電力を使う機械を作ってみましょう。
前回SharedPreferencesでテキストを保存というのをやりました。
SharedPreferencesはあくまで小規模なテキストなどの保存用で、画像などの大きなファイルの保存には向いていません。
大きなファイルの保存にはストリームを使います。
http://android.roof-balcony.com/shori/strage/localfile-2/
問題点は、ストリーム経由なのでめんどいのと、全部読み込みメソッドが何故か無いこと。
PHPで言うとfread()はあるのにfile_get_contents()が無い。
まあとりあえずやってみましょう。
pngファイルをビットマップとして開いてpngに変換してさらにバイト列にして保存とかがっかりにも程があるだろう。
なお、directory = "/data/data/" + this.getPackageName()はアプリのローカルディレクトリです。
ファイルエクスプローラーなどで確認できます。
特にパーミッションは指定していないのですが600だったので他のアプリから読まれる心配はない、のかなあ?
そこらへんよくわかりません。
さて、ファイルを保存する度にこんな面倒なことやってらんねえよ、ということでもう少しだけ簡単なメソッドが用意されています。
ファイルをストリームにする手間が省けただけで、画像をバイト列に変換する部分の野暮ったさはそのままです。
なお、書き込み先のディレクトリは"/data/data/" + this.getPackageName() + "/files/"で固定になり、サブディレクトリなどの指定はできません。
融通が利かない分、指定の必要もないため多少操作は楽になります。
でもね、本当にほしかったのはfilePutContents(String fileName, Bitmap bitmap)なんだよな。
いやまあ、メソッド作ればいいだけなのですが。
SharedPreferencesはあくまで小規模なテキストなどの保存用で、画像などの大きなファイルの保存には向いていません。
大きなファイルの保存にはストリームを使います。
http://android.roof-balcony.com/shori/strage/localfile-2/
問題点は、ストリーム経由なのでめんどいのと、全部読み込みメソッドが何故か無いこと。
PHPで言うとfread()はあるのにfile_get_contents()が無い。
まあとりあえずやってみましょう。
//画像を取得 Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.test); //画像をバイト列に ByteArrayOutputStream output = new ByteArrayOutputStream(); bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, output); byte[] byteArray = output.toByteArray(); //書き込むファイル String directory = "/data/data/" + this.getPackageName(); String filename = "fileName"; File file = new File(directory, filename); //ファイルをストリームに FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(file); //書き込みの実行 outputStream.write(byteArray); //読み込むファイル FileInputStream inputStream = new FileInputStream(file); //ストリームから画像に Bitmap bitmapFactory = BitmapFactory.decodeStream(inputStream); //ここからはImageViewに画像を突っ込んでるだけ View view = findViewById(R.id.imageView1); ImageView imageView = (ImageView)view; imageView.setImageBitmap(bitmapFactory);いやあ、これ絶対どこか間違ってるよ。
pngファイルをビットマップとして開いてpngに変換してさらにバイト列にして保存とかがっかりにも程があるだろう。
なお、directory = "/data/data/" + this.getPackageName()はアプリのローカルディレクトリです。
ファイルエクスプローラーなどで確認できます。
特にパーミッションは指定していないのですが600だったので他のアプリから読まれる心配はない、のかなあ?
そこらへんよくわかりません。
さて、ファイルを保存する度にこんな面倒なことやってらんねえよ、ということでもう少しだけ簡単なメソッドが用意されています。
//画像を取得 Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.test); ByteArrayOutputStream output = new ByteArrayOutputStream(); bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, output); byte[] byteArray = output.toByteArray(); //ファイル名 String filename =" fileName "; //書き込むストリーム OutputStream outputStream = openFileOutput(filename, Context.MODE_PRIVATE); //書き込み実行 outputStream.write(byteArray); //読み込み InputStream inputStream = openFileInput(filename); //ストリームから画像に Bitmap bitmapFactory = BitmapFactory.decodeStream(inputStream); //ここからはviewに画像を突っ込んでるだけ View view = findViewById(R.id.imageView1); ImageView imageView = (ImageView)view; imageView.setImageBitmap(bitmapFactory);openFileOutput()とopenFileInput()がそれなのですが……たいしてかわらないな。
ファイルをストリームにする手間が省けただけで、画像をバイト列に変換する部分の野暮ったさはそのままです。
なお、書き込み先のディレクトリは"/data/data/" + this.getPackageName() + "/files/"で固定になり、サブディレクトリなどの指定はできません。
融通が利かない分、指定の必要もないため多少操作は楽になります。
でもね、本当にほしかったのはfilePutContents(String fileName, Bitmap bitmap)なんだよな。
いやまあ、メソッド作ればいいだけなのですが。
スーパーマリオ3Dランド、クリア。
なにこの最終面超かっこいい。
なお、救済措置?を食らったのは7Wの砦だけでした。
スターメダルを積極的に狙ってないとはいえちょっと簡単すぎるな。
と思ったら現れる裏面!
マリオスタッフもびっくりなコースが揃ってるんだろうな!?
しかし裏面は今のところなんのために戦ってるのかわからないんだがどうするんだろう。
看板娘はさしおさえ2 鈴城 芹
看板娘はさしおさえ3
看板娘はさしおさえ4
☆☆☆
ほとんどさえじゃなくてとよの話になっとるがな。
基本的に毒にも薬にもならないまったり日常の話です。
と思ったらいきなり最後付近だけびっくり急展開。
インスタントブレイン
はい。
ギャルゲの積みゲが多すぎてどうにもこうにも。
蜂まで辿り着くのは何時のことになるのやら。
迷宮クロスブラッドリローデッド
前作に当たるところの「円卓の生徒」の音楽があまりにも神過ぎたので今作にも期待大にして不安も少々。
ていうか360版円卓のサントラ出してくれないかなあ。
なにこの最終面超かっこいい。
なお、救済措置?を食らったのは7Wの砦だけでした。
スターメダルを積極的に狙ってないとはいえちょっと簡単すぎるな。
と思ったら現れる裏面!
マリオスタッフもびっくりなコースが揃ってるんだろうな!?
しかし裏面は今のところなんのために戦ってるのかわからないんだがどうするんだろう。
看板娘はさしおさえ2 鈴城 芹
看板娘はさしおさえ3
看板娘はさしおさえ4
☆☆☆
ほとんどさえじゃなくてとよの話になっとるがな。
基本的に毒にも薬にもならないまったり日常の話です。
と思ったらいきなり最後付近だけびっくり急展開。
インスタントブレイン
はい。
ギャルゲの積みゲが多すぎてどうにもこうにも。
蜂まで辿り着くのは何時のことになるのやら。
迷宮クロスブラッドリローデッド
前作に当たるところの「円卓の生徒」の音楽があまりにも神過ぎたので今作にも期待大にして不安も少々。
ていうか360版円卓のサントラ出してくれないかなあ。
※以下はEE5.4.3の話なので、他のバージョンでは使用できなくなるかもしれません。
EquivalentExchange5.4.3は、等価交換というわりに一部等価でない変換法則があります。
一番わかりやすいところでは、
メビウス燃料*2→グロウストーン*8
グロウストーン*2→メビウス燃料*1
従って、このふたつを繰り返すだけでメビウス燃料が無限増殖。

・左上のチェストには賢者の石をひとつ
・左上の全自動作業台には賢者の石をひとつとグロウストーン*2(メビウス燃料のレシピ)
・右下のチェストには賢者の石をひとつ
・右下の全自動作業台には賢者の石をひとつとメビウス燃料*2(グロウストーンのレシピ)
あとは素材となるグロウストーンを幾つか放り込んで、しばらく放置しているだけでグロウストーンが大量に。
増加ペースがグロウストーンの方が多いので、最後は右下の全自動作業台を無効化すれば残ったグロウストーンが全部メビウス燃料になります。
消費が一切無い、かつ素材調達も用意、時間もこちらのほうが圧倒的に短いと、コレクターによる精製よりも遙かに有利です。
他にも砂→ガラス*3(精製で砂*3)、ラピスラズリ*3→染料(ライム)*3→サボテン*12→染料*12→ラピスラズリ*12、といった増殖レシピがいくつもあるんだけど、仕様なんだかバグなんだか。
EquivalentExchange5.4.3は、等価交換というわりに一部等価でない変換法則があります。
一番わかりやすいところでは、
メビウス燃料*2→グロウストーン*8
グロウストーン*2→メビウス燃料*1
従って、このふたつを繰り返すだけでメビウス燃料が無限増殖。
・左上のチェストには賢者の石をひとつ
・左上の全自動作業台には賢者の石をひとつとグロウストーン*2(メビウス燃料のレシピ)
・右下のチェストには賢者の石をひとつ
・右下の全自動作業台には賢者の石をひとつとメビウス燃料*2(グロウストーンのレシピ)
あとは素材となるグロウストーンを幾つか放り込んで、しばらく放置しているだけでグロウストーンが大量に。
増加ペースがグロウストーンの方が多いので、最後は右下の全自動作業台を無効化すれば残ったグロウストーンが全部メビウス燃料になります。
消費が一切無い、かつ素材調達も用意、時間もこちらのほうが圧倒的に短いと、コレクターによる精製よりも遙かに有利です。
他にも砂→ガラス*3(精製で砂*3)、ラピスラズリ*3→染料(ライム)*3→サボテン*12→染料*12→ラピスラズリ*12、といった増殖レシピがいくつもあるんだけど、仕様なんだかバグなんだか。
